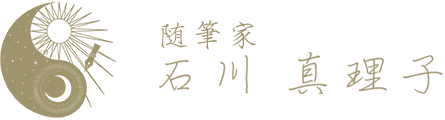よく斬れる日本刀のようでありたい
二十代半ばには、作家としての矜持について、はっきりした志向を持っていました。
たぶん作家でもあった父の影響が大きいのだと思います。
私としては、自分のことを作家というのは、なんとなく口幅ったい感じがしますので、ここでは「物書」という言葉に置き換えました。
物書というのは、物を書いていないときでも物書です。
物を書いているときだけが物書としての自分になっているとしたら、すぐに種は尽きてしまうことでしょう。
物書は枯れない泉を持たねば、とうてい続くものではありません。
それには食べているときも寝ているときも、どんなときであろうとも物書であることです。
つまり二十四時間のすべてが、筆を執るその時に繋がっているのです。
二十四時間のすべてが筆を執るときに繋がっているということは、いかに過ごしているかということが重大な問題となってきます。
ただ漠然と、漫然と時を過ごしているとしたら、いざ筆を執ったときにそれは露呈することでしょう。間違いなく。
多くの人をごまかし仰せても、見る目のある人が見ればわかってしまいます。
自分というものが人生における主人公であるというこの厳しい事実とがっぷり四つに取り組んで、その一挙手一投足を通じて自分を鍛錬すれば、筆を執るとおのずからそれは光となって顕れるものです。
日本刀は火の中にくべ真っ赤になったところを叩かれて叩かれて叩かれ尽くし、仕舞には水に浸けられ、ようやく鈍色の深みのある光を放ちます。
物書というのは、よく斬れる日本刀のようでありたいものです。
つまり「己に徹するということ」、ここにすべてが集約されていきます。
何ごとも「己に徹すること」に集約される
もっとも、己に徹するということは、何も物書に限られたことではありません。
すべてのことに共通する重大かつ重要な真理なのです。
あらゆる事物が己に帰結していくことを思えば、生き方の基本がそうならざるをえなくなるものでしょう。
それくらい真剣になると、かえって肩の力が抜けるものです。
つまり丹田に気が落ち着き、体の中心に軸ができるので自由を得るのです。
自然、ストレスを感じにくくなります。
こうして泉は枯れることを知らず、いつでも透明な水を満々とたたえては、その時々の空を映しながら、まるで音楽のような水音を立てて流れ出していくようになるのです。
こうして綴られた言葉こそ、魂が宿っている。
そう信じています。